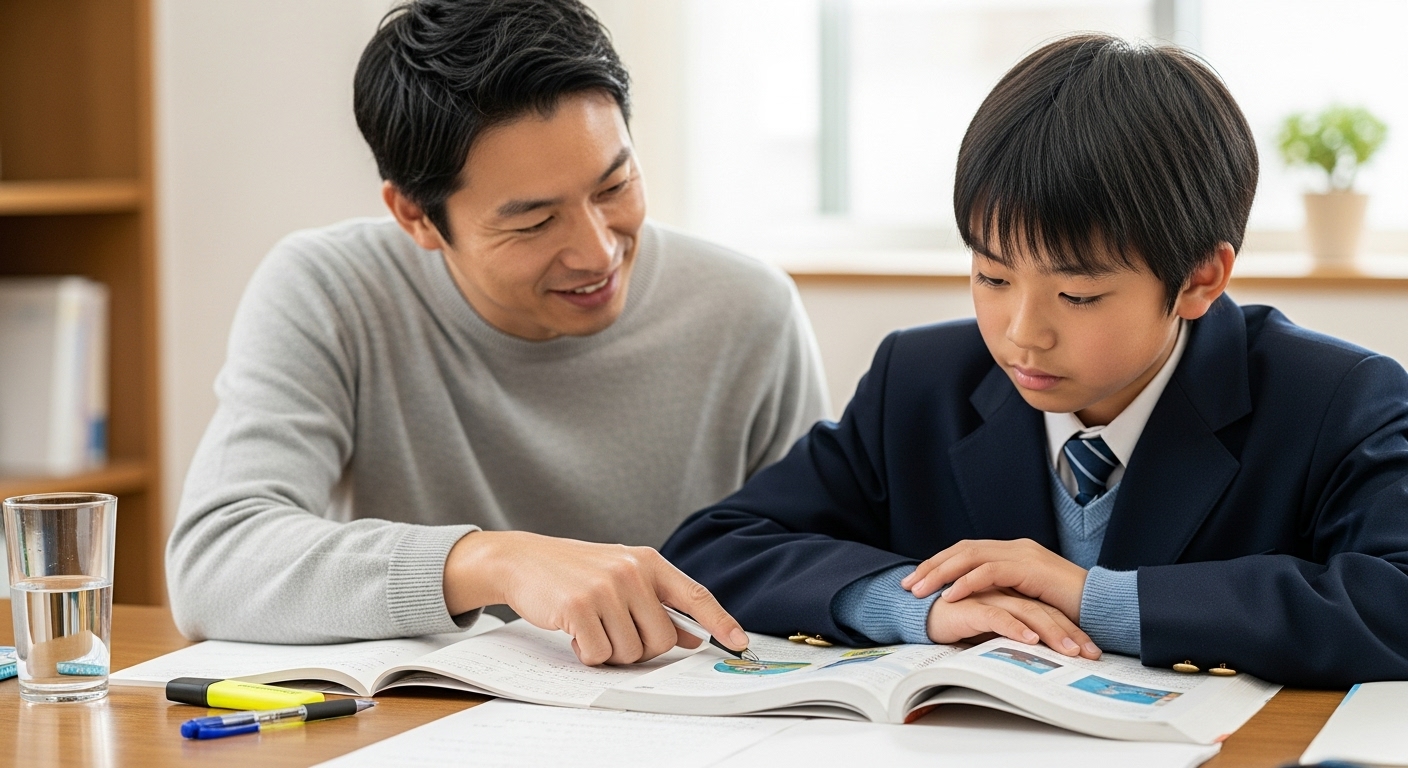
はじめに:すべての学びの土台となる国語力
「うちの子、数学の文章題が解けないんです」 「英語の長文読解になると、途端に点数が下がって…」
このようなご相談を、私たち至知ゼミナールでは日々たくさんいただきます。実は、これらの悩みの根本原因は「国語力不足」にあることがとても多いのです。
現代社会では、膨大な情報があふれています。その中から正しい情報を読み解き、自分の考えを論理的に相手に伝える力が、これまで以上に求められています。この力こそが「国語力」なのです。
国語力とは、単に国語のテストで良い点を取る力ではありません。文章を正確に理解する「読解力」と、自分の考えを的確に表現する「表現力」、この二つが組み合わさった総合的な力を指します。
中学生や高校生の皆さんにとって、国語力はすべての教科の基礎となります。数学の応用問題を理解するにも、社会科で歴史の因果関係を把握するにも、理科の実験結果を考察するにも、国語力が必要です。さらに、大学受験では小論文や面接で国語力が直接問われます。
本記事では、個別指導を専門とする私たち至知ゼミナールが、なぜ今国語力が必要なのか、そしてどのように国語力を鍛えていくべきかを、具体的な指導事例を交えながら詳しくお伝えします。
第1章:中学生・高校生にとっての国語力の重要性
中学生にとっての国語力—すべての教科の土台
中学生の時期は、学習内容が一気に高度になる重要な転換期です。この時期に国語力をしっかり身につけておかないと、後々大きな学力差となって現れます。
例えば、数学の文章題を見てみましょう。「A君は家から駅まで分速80メートルで歩き、B君は3分後に分速120メートルで追いかけた」という問題文があったとします。この問題が解けない生徒の多くは、実は計算力ではなく、問題文を正確に理解する読解力が不足しているのです。
「3分後に」という言葉が何を意味するのか、「追いかけた」という表現から何を読み取るべきか。こうした言葉の意味を正確に把握できなければ、どんなに計算が得意でも正解にたどり着けません。
理科や社会でも同様です。「光合成において、葉緑体が光エネルギーを化学エネルギーに変換する」という説明文を読んだとき、主語と述語の関係、因果関係を正しく理解できなければ、その現象を本質的に理解することはできません。
至知ゼミナールの個別指導では、こうした他教科での読解力の問題も、国語力の視点から分析します。実際に、数学の成績が伸び悩んでいた中学2年生の生徒が、国語の読解訓練を並行して行った結果、3ヶ月後には数学の文章題の正答率が大幅に向上した事例もあります。
高校生にとっての国語力—大学受験を突破する専門的な力
高校生になると、国語力はさらに専門的で実践的な力として磨かれる必要があります。なぜなら、大学受験では国語力が直接的に問われる場面が増えるからです。
特に重要なのが小論文です。多くの大学入試で課される小論文は、単に文章が書けるだけでは合格点に達しません。課題文を正確に読み解き、その内容を踏まえて自分の意見を論理的に構成し、説得力のある文章で表現する。この一連のプロセスすべてに、高度な国語力が必要なのです。
ある高校3年生の生徒は、志望大学の小論文対策で苦戦していました。「自分の意見は書けるのですが、なぜかいつも評価が低いんです」という相談でした。その生徒の答案を見ると、確かに自分の考えは書かれていましたが、課題文の内容を踏まえておらず、論理の飛躍も見られました。
私たちは、まず課題文を丁寧に読み解く訓練から始めました。筆者の主張は何か、どのような根拠でその主張を支えているか、論理構造を図式化して理解する練習です。その上で、自分の意見をどう構成するかを段階的に指導しました。結果として、その生徒は見事に第一志望校に合格しました。
面接でも国語力は欠かせません。面接官の質問を正確に理解し、自分の考えを簡潔かつ論理的に伝える。この能力も、日頃から国語力を鍛えていなければ身につきません。
英語学習にも影響する国語力
意外に思われるかもしれませんが、英語の成績向上にも国語力が大きく関係しています。英語の長文読解で苦労している生徒の多くは、実は日本語での読解力にも課題があることが少なくありません。
英文を読む際、私たちは無意識のうちに日本語に置き換えながら理解しています。その際、日本語での論理的思考力や文章構造の理解力が不足していると、英文の内容も正しく把握できないのです。
至知ゼミナールでは、英語の指導においても、必要に応じて日本語での論理的思考力を鍛える指導を組み込みます。文の構造を理解する力、段落同士のつながりを把握する力など、言語を超えた普遍的な読解力を育てることで、英語力も同時に向上させることができます。
第2章:読解力を鍛える具体的な方法
読解力とは何か—表面を読むだけでは不十分
読解力というと、多くの方は「文章を読んで内容を理解する力」と考えます。しかし、本当の読解力はそれだけではありません。
真の読解力とは、文章の表面的な意味だけでなく、筆者の意図、論理構造、行間に隠された意味まで読み取る力です。例えば、新聞の社説を読むとき、単に「こういうことが書いてある」と理解するだけでなく、「なぜ筆者はこの主張をするのか」「どのような前提に立っているのか」「この主張の根拠は十分か」まで考えられることが、高度な読解力といえます。
中学生や高校生の多くは、文章を読む際に「何が書いてあるか」だけに注目し、「なぜそう書いてあるのか」「筆者は何を伝えたいのか」という深い部分まで考えることが少ないのです。
論理構造を可視化する訓練
至知ゼミナールの個別指導では、文章の論理構造を図式化する訓練を重視しています。これは、文章全体の構造を視覚的に理解するための方法です。
具体的には、文章を「筆者の主張」「根拠となる事実やデータ」「具体例」「反論への対処」「結論」といった要素に分解します。そして、それぞれの要素がどのようにつながっているかを図で表すのです。
例えば、ある評論文で「現代社会ではコミュニケーション能力が重要である」という主張があったとします。この主張を支える根拠として「グローバル化による多様性の増加」「チームワークの重要性」などが挙げられているかもしれません。さらに、具体例として「企業での採用基準の変化」が示されているかもしれません。
こうした構造を図式化することで、文章全体の流れが明確になり、筆者の論理展開を正確に理解できるようになります。最初は時間がかかりますが、繰り返し練習することで、文章を読みながら自然に構造を把握できるようになります。
行間を読む力を育てる
文章には、明示的に書かれていない情報も多く含まれています。この「書かれていないこと」を読み取る力が、行間を読む力です。
例えば、小説で「彼は黙って窓の外を見つめた」という一文があったとします。この一文から、登場人物の心情や状況をどれだけ読み取れるでしょうか。「黙って」という言葉には、何か言いたいことがあるのに言えない、あるいは考え込んでいる様子が暗示されているかもしれません。「窓の外」を見ているということは、現実から目を逸らしたい、あるいは答えを探している可能性もあります。
このように、直接書かれていない情報を想像し、推測する力を養うことで、文章の理解は格段に深まります。至知ゼミナールでは、生徒と対話しながら「この表現から何が読み取れるか」「なぜ筆者はこの言葉を選んだのか」を一緒に考えていきます。
個別指導だからこそできる細やかなフィードバック
読解力を伸ばす上で最も重要なのが、適切なフィードバックです。生徒が文章を読み違えた時、なぜそのような読み違いをしたのかを分析し、正しい読み方を示すことが不可欠です。
集団授業では、一人ひとりの読み違いの原因を詳しく分析する時間はなかなか取れません。しかし、個別指導なら可能です。至知ゼミナールでは、生徒が問題を解いた後、必ず「なぜそう考えたのか」を聞きます。
ある中学3年生の生徒は、評論文の問題でいつも筆者の主張とは逆の選択肢を選んでしまう傾向がありました。詳しく話を聞くと、その生徒は具体例の部分に注目しすぎて、筆者の本当の主張を見失っていることが分かりました。そこで、「主張」と「具体例」の関係を丁寧に説明し、主張を見つける練習を繰り返しました。すると、2ヶ月後には正答率が大きく改善したのです。
このように、一人ひとりの思考プロセスに寄り添い、的確なアドバイスを提供できることが、個別指導の最大の強みです。
第3章:表現力を高める実践的トレーニング
表現力の重要性—考えを正確に伝える力
「分かっているのに説明できない」「書こうとすると言葉が出てこない」こうした悩みを持つ生徒は非常に多くいます。これは表現力の不足が原因です。
表現力とは、自分の考えや知識を、他者に分かりやすく正確に伝える力です。大学受験の小論文や面接では、この表現力が直接評価されます。また、社会に出てからも、自分の意見をプレゼンテーションしたり、レポートにまとめたりする場面で必要不可欠な力です。
表現力を高めるには、読解力とは異なるトレーニングが必要です。読むことと書くこと・話すことは、全く別の技能だからです。
論理的な文章構成を身につける
表現力の基礎となるのが、論理的な文章構成力です。どんなに良い考えを持っていても、それを論理的に整理して伝えられなければ、相手には伝わりません。
至知ゼミナールの小論文対策では、まず基本的な文章構成を徹底的に訓練します。序論で問題提起をし、本論で自分の主張とその根拠を示し、結論でまとめる。このシンプルな構成を、繰り返し練習することで身体に染み込ませるのです。
ある高校2年生の生徒は、小論文を書くと話があちこちに飛んでしまい、まとまりのない文章になっていました。そこで、まず「言いたいことを一文で表す」練習から始めました。自分の主張を最も簡潔に表現できる一文を考え、それを軸に文章を組み立てていく。この訓練を重ねることで、その生徒の小論文は見違えるほど論理的になりました。
言葉の選択と表現の精度を上げる
同じことを伝えるにも、使う言葉によって印象や正確さが大きく変わります。曖昧な表現を避け、正確な言葉を選ぶ訓練も重要です。
例えば、「環境問題は深刻だ」という表現と、「地球温暖化による異常気象の頻発は、人類の生存基盤を脅かす深刻な問題である」という表現では、具体性と説得力が全く違います。
至知ゼミナールでは、生徒が書いた文章を一緒に読みながら、「この表現はもっと具体的にできないか」「別の言葉に置き換えたらどうなるか」と問いかけます。こうした対話を通じて、言葉の選択に対する意識が高まっていきます。
面接対策での表現力訓練
面接は、口頭での表現力が試される場です。限られた時間の中で、自分の考えを分かりやすく、かつ印象的に伝えなければなりません。
面接対策では、まず自分の考えを整理する訓練から始めます。「なぜこの大学を志望するのか」という問いに対して、漠然と「興味があるから」と答えるのではなく、具体的なエピソードを交えて論理的に説明できるように準備します。
ある高校3年生の生徒は、面接練習で緊張のあまり言葉が出なくなってしまうことがありました。そこで、まず自分の考えを箇条書きで整理し、それを元に何度も話す練習を重ねました。さらに、想定される質問に対する答えを準備し、実際に声に出して練習することで、本番では自信を持って答えられるようになりました。
面接での表現力は、一朝一夕には身につきません。だからこそ、早い段階から計画的に準備を進めることが大切なのです。
第4章:至知ゼミナールの国語力育成への取り組み
一人ひとりに合わせた個別カリキュラム
至知ゼミナールの個別指導の最大の特徴は、生徒一人ひとりの課題に合わせてカリキュラムを組むことです。
国語力の課題は、生徒によって全く異なります。読解のスピードが遅い生徒、論理構造の把握が苦手な生徒、語彙力が不足している生徒、表現が曖昧になりがちな生徒など、その状況は様々です。
私たちは、まず学習相談の段階で、生徒の現状を詳しくヒアリングします。どの科目でどのような困難を感じているか、国語のどの分野が苦手か、将来どのような進路を考えているか。これらの情報を総合的に分析し、その生徒に最適な指導プランを作成します。
例えば、理系志望で小論文対策が必要な生徒には、論理的な文章構成を重点的に指導します。一方、文系志望で古典が苦手な生徒には、古文の読解方法を基礎から丁寧に教えます。こうした柔軟な対応ができるのが、個別指導の強みです。
確かな実績に裏付けられた指導力
私たち至知ゼミナールは、これまで多くの生徒を志望校合格へと導いてきました。令和7年度の大学受験では、小論文や面接が課される大学にも多数の合格者を輩出しています。
また、公立高校入試でも、愛知校舎・岐阜校舎ともに高い合格実績を残しています。これらの実績は、国語力を含めた基礎学力をしっかりと育成してきた結果です。
国語力の向上は、短期間で目に見える成果が出にくい分野です。しかし、長期的に見れば、すべての学力の土台となる最も重要な力です。私たちは、この国語力育成に真剣に取り組み、確かな成果を上げてきました。
安心して学べる環境づくり
至知ゼミナールは、生徒が安心して学べる環境づくりにも力を入れています。
私たちは、SDGs事業認定を取得し、教育を通じた社会貢献を目指しています。また、「健康宣言チャレンジ事務所」「職場環境改善宣言企業」にも認定されており、講師が安定して質の高い指導を提供できる環境が整っています。
さらに、名古屋グランパスの和泉竜司氏や上田桃夏氏がスペシャルサポーターとして、受験生を応援してくれています。彼らの「継続する力」や「目標達成への情熱」は、長期的な学習を続ける生徒たちにとって、大きな励みとなっています。
通いやすさと経済的な配慮
国語力の育成には、継続的な学習が欠かせません。そのため、通いやすさと経済的な負担の軽減も重要です。
至知ゼミナールは、個別指導でありながら安心納得の価格設定を実現しています。質の高い指導を、できるだけ多くの生徒に届けたいという思いからです。
また、地域に根差した展開も進めており、2025年6月には鶉校(岐阜校舎)が、5月には扶桑校(愛知校舎)が新規開校しました。お住まいの地域から通いやすい教室で、質の高い個別指導を受けていただけます。
まとめ:国語力という一生の財産を育てる
国語力は、単なる受験のための学力ではありません。それは、人生を通じて活用できる一生の財産です。
情報を正確に読み解き、自分の考えを論理的に表現する力は、どのような進路を選んでも必要とされます。大学での学び、社会に出てからの仕事、日常生活でのコミュニケーション、あらゆる場面で国語力は役立ちます。
中学生・高校生の時期は、この国語力を本格的に育てる最適なタイミングです。この時期にしっかりとした基礎を築いておけば、その後の学びや成長が大きく変わってきます。
至知ゼミナールは、一人ひとりの生徒に寄り添い、その生徒に最適な方法で国語力を育成します。個別指導だからこそできる、きめ細やかなサポートで、お子様の可能性を最大限に引き出します。
現在、新規入塾生募集キャンペーンを実施中です。まずは無料体験や学習相談をご利用いただき、私たちの指導を実際に体感してください。お申し込みは簡単2分で完了します。
国語力を鍛え、未来を切り拓く力を育てる。その第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか。
どんなお悩みでも構いません。お気軽にご相談ください。 お問い合わせは、総合受付(0120-63-1119)まで。年中無休で10時から22時まで対応しております。









