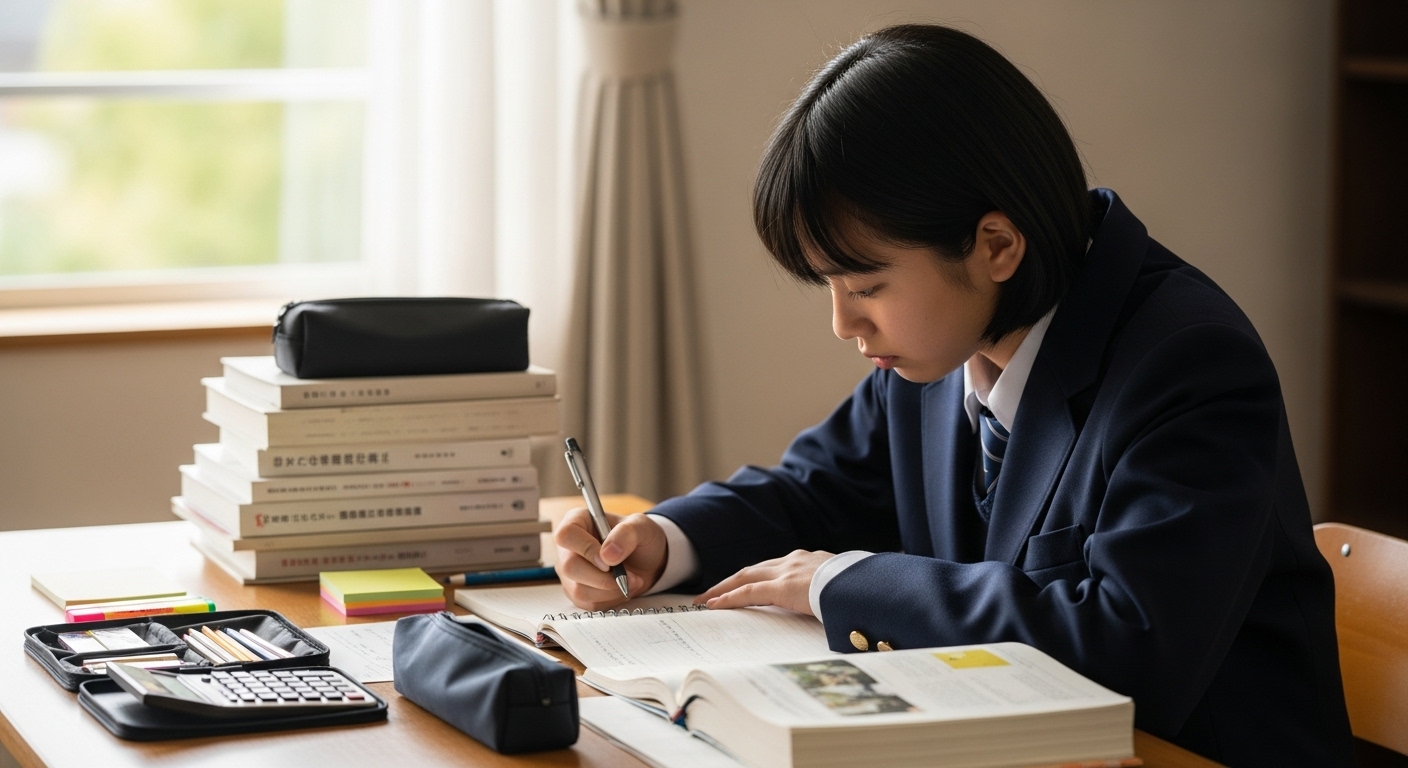
こんにちは。個別指導の至知ゼミナールです。
長年、多くの生徒さんを指導してきた中で、保護者の方から「うちの子はなぜ勉強ができないのでしょうか」というご相談をたくさんいただきます。同じ授業を受けているのに、成績に大きな差が出てしまうのはなぜなのか。今回は、勉強ができる子とできない子の違いについて、私たちの指導経験をもとに詳しく解説していきます。
勉強ができる子に共通する学習習慣
勉強ができる子には、明確な共通点があります。それは「毎日の学習習慣」が身についているということです。
当塾に通う優秀な生徒さんたちを見ていると、必ず毎日決まった時間に机に向かっています。たとえば、中学2年生のAさんは、夕食後の19時から21時までを勉強時間と決めています。部活で疲れた日も、この時間だけは必ず確保しているのです。
「習慣化」とは、意識しなくても自然と行動できる状態のことを指します。歯磨きのように、やらないと気持ち悪いと感じるレベルまで習慣が定着すると、勉強も苦にならなくなります。
成績上位の生徒さんたちは、次のような特徴を持っています。
まず、学習時間が固定されています。毎日同じ時間に勉強することで、脳がその時間を「学習モード」として認識するようになります。朝型の子もいれば夜型の子もいますが、大切なのは自分に合った時間を見つけることです。
次に、学習環境を整えています。机の上には必要な教材だけを置き、スマートフォンは別の部屋に置くなど、集中できる環境づくりを徹底しています。
さらに、復習を欠かしません。その日学んだことをその日のうちに見直す習慣があります。授業で習った内容を帰宅後すぐにノートを見返すだけでも、記憶の定着率は大きく変わってきます。
また、計画性を持って取り組んでいます。テスト前だけでなく、日頃から計画的に学習を進めています。週末には次の週の予定を立て、どの教科をいつ勉強するか決めているのです。
私たちの塾では、こうした学習習慣を身につけるためのサポートを行っています。最初は30分からでも構いません。少しずつ学習時間を延ばしていくことで、無理なく習慣化することができます。
勉強ができない子が抱える学習の課題
一方で、成績が伸び悩んでいる生徒さんにも共通する特徴があります。
最も多いのが、学習時間の不規則さです。気分が乗った時だけ勉強する、テスト前だけ詰め込むといった学習パターンでは、知識が定着しません。
当塾に入塾されたBくんの例をご紹介しましょう。入塾時、Bくんは「勉強はしているのに成績が上がらない」と悩んでいました。詳しく話を聞いてみると、勉強時間は確かにあるものの、スマートフォンを見ながら、音楽を聴きながらといった「ながら勉強」をしていたのです。
集中力が続かないというのも大きな課題です。10分勉強しては休憩、また10分勉強しては別のことを始めるという状態では、深い理解には至りません。
基礎知識の不足も見逃せません。応用問題に取り組もうとしても、基礎が固まっていなければ解けるはずがありません。数学で言えば、計算の基礎ができていないのに方程式の文章題に挑戦しても、つまずいてしまうのは当然です。
復習をしない、または復習の仕方がわからないという問題もあります。授業を受けただけで満足してしまい、後から見直すことをしないため、せっかく学んだ内容が記憶に残らないのです。
質問ができないことも成績が伸びない要因の一つです。わからないことがあっても、恥ずかしくて質問できない、何がわからないのかすらわからないという状態では、学習の効率が下がってしまいます。
これらの課題は、適切な指導と環境があれば必ず改善できます。私たちは一人ひとりの課題を見極め、その子に合った学習方法を提案しています。
家庭環境が学習習慣に与える影響
勉強ができる子とできない子の差は、実は家庭環境にも大きく左右されます。
ここで言う家庭環境とは、経済的な豊かさではありません。学習を支える環境が整っているかどうかということです。
当塾の保護者面談でよく感じるのは、成績が良い生徒さんのご家庭では、学習を大切にする雰囲気があるということです。
例えば、Cさんのご家庭では、夕食後の時間は家族全員が静かに過ごすルールがあります。お父様は読書、お母様は家事や趣味の時間、そしてCさんは勉強という具合です。家族が同じ空間で静かに集中する時間を共有することで、自然と勉強する習慣が身についたそうです。
物理的な学習スペースの確保も重要です。必ずしも個室が必要というわけではありませんが、落ち着いて勉強できる場所があることが大切です。リビングの一角でも、照明が適切で、静かな時間を確保できれば十分です。
保護者の方の関わり方も影響します。ただし、これは過干渉という意味ではありません。適度な関心を持ち、子どもの頑張りを認めてあげることが重要なのです。
「今日は何を勉強したの」と聞くよりも、「今日も勉強頑張っていたね」と声をかける方が、子どものモチベーションは上がります。結果だけでなく、過程を認めることが大切です。
また、生活リズムの安定も学習に大きく影響します。毎日同じ時間に起きて、同じ時間に寝る。規則正しい生活が、集中力や記憶力を高めます。睡眠不足の状態では、どんなに時間をかけても学習効率は上がりません。
家族の会話の中で学習の話題が自然に出てくることも、学習意欲を高める要因になります。ニュースについて話し合ったり、わからないことを一緒に調べたりする経験が、学ぶことへの興味を育てます。
モチベーションの違いが成績を分ける
勉強に対するモチベーション、つまり「やる気」の持ち方も、成績に大きく影響します。
成績が良い生徒さんは、明確な目標を持っています。「〇〇高校に合格したい」「将来は〇〇になりたい」といった具体的な目標があると、日々の勉強に意味を見出すことができます。
当塾に通うDくんは、中学1年生の時に参加した職場体験で建築士という仕事に興味を持ちました。それから数学と理科を特に頑張るようになり、成績が大幅に上がりました。目標ができたことで、勉強する理由が明確になったのです。
一方で、「なぜ勉強しなければいけないのか」という疑問を持ったまま机に向かっている生徒さんもいます。これでは集中力も続きませんし、学習内容も頭に入りません。
目標は大きなものである必要はありません。「次のテストで数学を10点上げる」「英単語を毎日10個覚える」といった小さな目標でも十分です。大切なのは、達成可能な目標を設定し、それをクリアする喜びを味わうことです。
成功体験の積み重ねも重要です。小さな成功でも、それを積み重ねることで自信につながります。「できた」という経験が、次の挑戦への意欲を生み出すのです。
私たちの塾では、一人ひとりに合った目標設定をサポートしています。大きすぎる目標は挫折の原因になりますし、簡単すぎる目標では成長につながりません。その子の現在の学力と性格を考慮して、適切な目標を一緒に考えていきます。
また、褒めることの大切さも忘れてはいけません。結果だけでなく、努力の過程を認めることで、子どもは「もっと頑張ろう」という気持ちになります。間違えた問題があっても、「ここまで解けたね」と途中までの頑張りを認めることが、次への意欲につながります。
効果的な学習方法を知っているかどうか
同じ時間勉強しても、成績に差が出るのは学習方法の違いによるところが大きいです。
効果的な学習方法を知っている生徒さんは、短時間でも大きな成果を上げます。逆に、非効率な方法で長時間勉強しても、疲れるばかりで成績は伸びません。
当塾でよく見かけるのは、教科書を何度も読むだけという学習方法です。確かに読むことは大切ですが、ただ目で追っているだけでは記憶に残りにくいのです。
効果的な学習方法の一つが「アウトプット学習」です。これは、学んだ内容を自分の言葉で説明したり、問題を解いたりすることを指します。インプット、つまり教科書を読んだり授業を聞いたりするだけでは、知識は定着しません。
例えば、歴史を学ぶ際、教科書を読むだけでなく、ノートに年表を自分で作ってみる。数学なら、例題を見るだけでなく、実際に問題を解いてみる。こうしたアウトプットを通じて、初めて知識が自分のものになります。
復習のタイミングも重要です。人間の記憶は時間とともに忘れていくものですが、適切なタイミングで復習することで、記憶の定着率が高まります。
効果的な復習のタイミングは、まず授業を受けたその日のうちに一度見直すこと。次に1週間後、そして1ヶ月後と、徐々に間隔を空けて復習すると、長期記憶として定着します。
ノートの取り方も学習効果に影響します。黒板を丸写しするのではなく、重要なポイントを自分なりにまとめる。色分けをして見やすくする。後から見返した時に理解できるようなノート作りが大切です。
問題演習の仕方も工夫が必要です。間違えた問題をそのままにせず、なぜ間違えたのかを分析する。同じタイプの問題をもう一度解いてみる。こうした丁寧な学習が、確実な実力につながります。
私たちの塾では、ただ教えるだけでなく、効果的な学習方法そのものを指導しています。魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えることが、本当の学力向上につながると考えているからです。
個別指導だからこそできるサポート
個別指導の至知ゼミナールでは、一人ひとりの特性に合わせた指導を行っています。
集団授業では、どうしてもペースについていけない生徒さんや、逆に物足りなく感じる生徒さんが出てきます。個別指導なら、その子のペースで、その子に必要な内容を学ぶことができます。
入塾時には必ず面談を行い、現在の学力、学習習慣、目標などを詳しくお伺いします。その上で、一人ひとりに最適な学習計画を立てていきます。
例えば、基礎が不足している生徒さんには、学年を戻って復習することもあります。中学3年生でも、必要なら中学1年生の内容から丁寧に学び直します。恥ずかしいことではありません。確実に理解することが、将来の成績向上につながるのです。
逆に、学校の授業が簡単すぎると感じている生徒さんには、応用問題や発展的な内容を提供します。その子の可能性を最大限に引き出すことが私たちの役目です。
質問しやすい環境づくりも個別指導の強みです。大勢の前では恥ずかしくて質問できないという生徒さんも、マンツーマンなら気兼ねなく質問できます。わからないことをわからないままにしないことが、学力向上の第一歩です。
また、学習習慣の定着もサポートしています。宿題の量や内容も、その子の状況に合わせて調整します。最初は少なめでも、徐々に増やしていくことで、無理なく学習習慣が身につきます。
保護者の方との連携も大切にしています。定期的な面談で学習状況をお伝えし、ご家庭でのサポート方法についてもアドバイスさせていただきます。塾と家庭が協力することで、より効果的な学習環境を作ることができます。
私たちは、すべての生徒さんに可能性があると信じています。今は成績が伸び悩んでいても、適切な指導と環境があれば必ず変われます。一人ひとりの成長を見守り、支えていくことが、個別指導の至知ゼミナールの使命です。
もし、お子様の学習についてお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。無料体験授業も実施しております。お子様に合った学習方法を一緒に見つけていきましょう。









